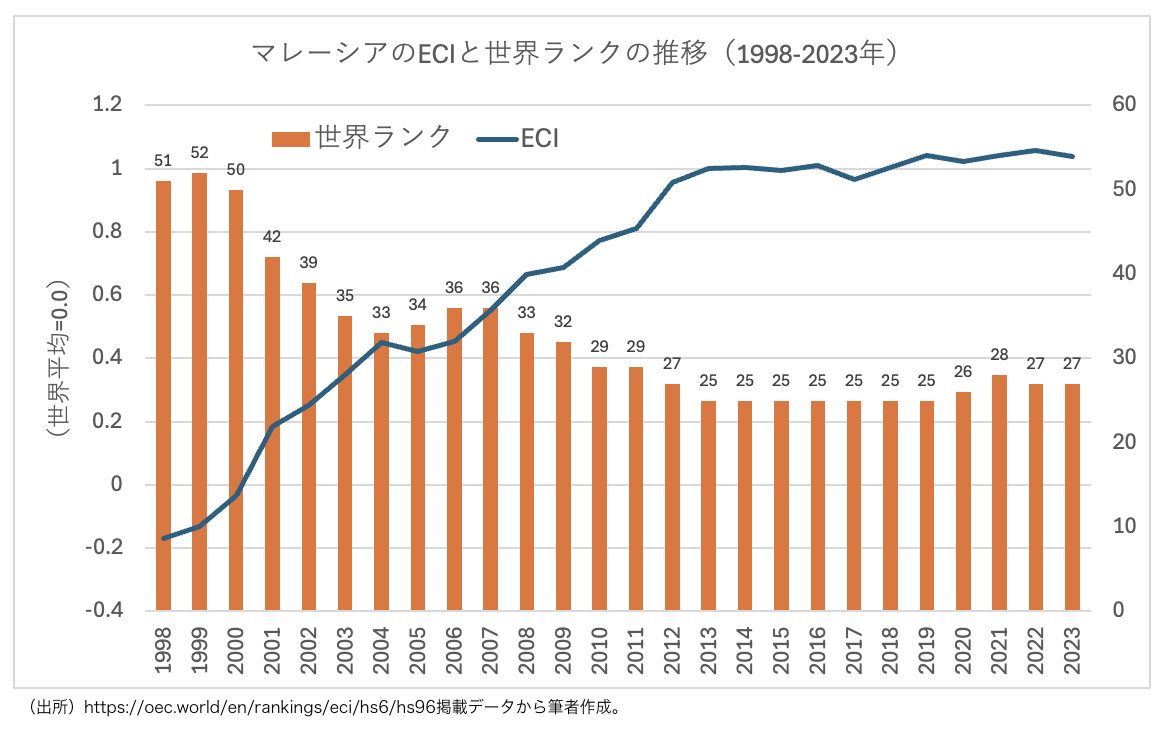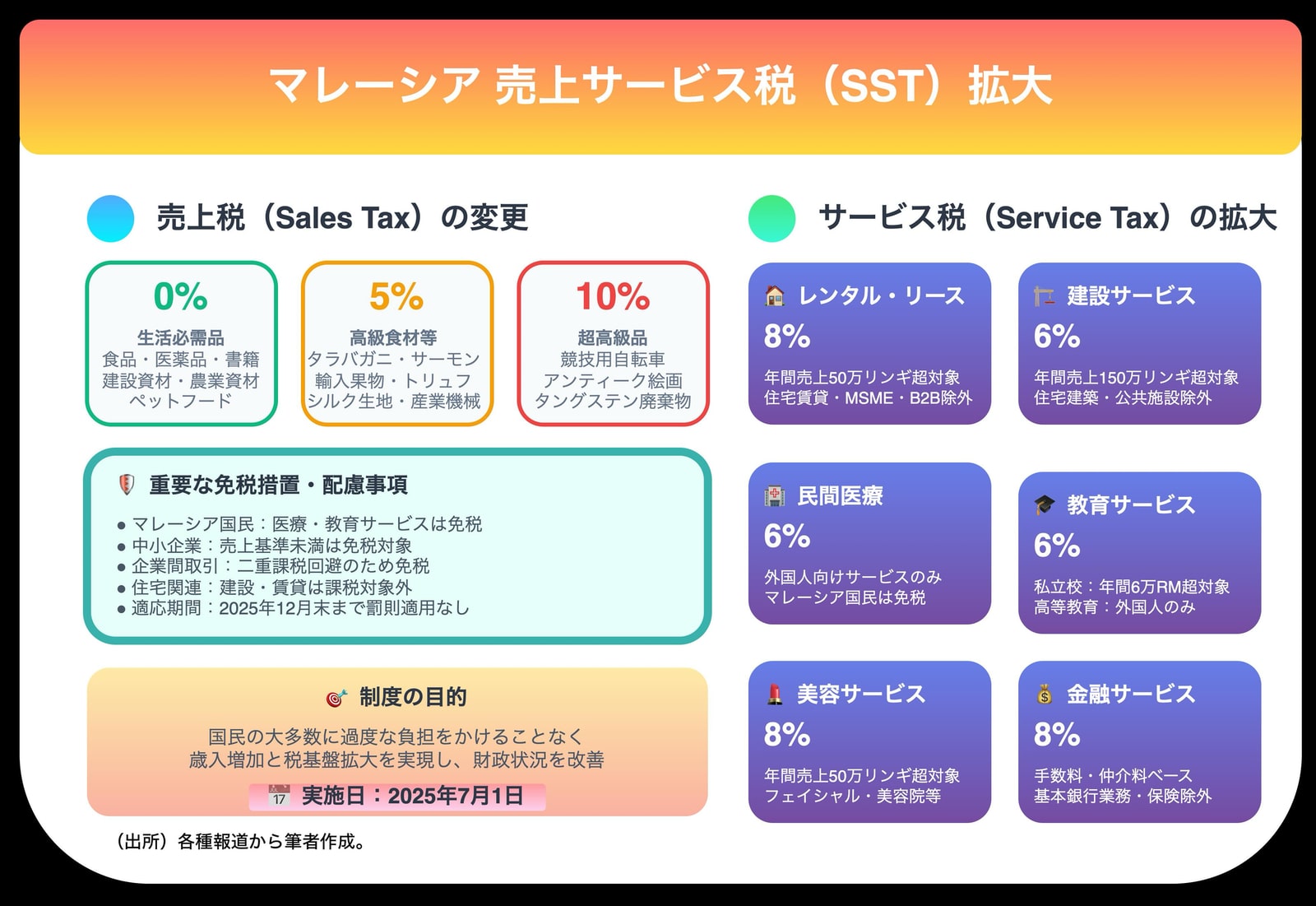第903回:中小企業の両利き経営(6)両利きとオープンイノベーション
前回は、両利きであることが一企業の短期的な売上に直接つながらないとしても、国全体、あるいは地球規模で取り組むことが合理的な場合があるというお話でした。今回からは、中小企業が両利きを達成するための条件について検討します。今回は、オープンイノベーションによる両利きについてです。
内部リソースの不足を克服し、両利きになるために、中小企業は外部リソースに依存する必要があります。外部リソースを活用したイノベーションは、オープンイノベーションと呼ばれます。オープンイノベーションの目的は、大企業と中小企業とで異なることが多く、大企業はパートナーの資産や能力を活用するためにオープンイノベーションを採用するのに対し、中小企業は内部資産の不足を補うためにオープンイノベーションに頼る傾向があります。中小企業は通常、財務および人的資本リソース、管理および技術スキル、ノウハウ等の重大な不足に悩まされており、そのため、ネットワーキングを、技術力を拡大する手段と見なしています。外部とのコラボレーションを活用することで、中小企業はイノベーション投資に関連するコストを削減し、イノベーションプロセスをうまく適応および再構成することができます。オープンイノベーションを含む外部組織との協働は、イノベーション活動のポートフォリオを拡大し、知識の補完性を高め、生産性を向上させるための優れたアプローチであり、ひいては中小企業のイノベーション能力にプラスの影響を与えます。オープンイノベーションを導入することで、中小企業は既存の能力、資源、組織構造を活用し、既に信頼されている関係ネットワークを強化し、財務的な利益を得ることができます。
特定の地域に関心を持たず、最適な立地を求めて移動する多国籍企業とは対照的に、中小企業は、歴史的に特定の場所や地元住民と何世代にもわたって結びついていることが多いようです。例えば、世界的なドイツ中小企業の 70% が拠点を置く BW 州、バイエルン州、ノルトライン=ヴェストファーレン州の中小企業は、影響力のある特定の地域のソーシャルキャピタルの文脈に根ざし、周辺のコミュニティ、企業、大学とのつながりを活用して国際市場に効果的に参入しています。このように、中小企業は、地域ネットワークを活用してオープンイノベーションを実施できるという点で有利である可能性があります。例えば、タイの 6 つの地域の中小企業 615 社を対象とした研究では、オープンイノベーションの実施と両利きのイノベーションの実践との間に有意な正の相関関係が見つかり、オープンイノベーションの採用が両利きのイノベーションを強化できることを示唆しています。
しかし、オープンイノベーションはしばしばオーケストレーションを伴います。オープンイノベーションを展開するコストは、特に資金が限られている中小企業にとって重要な考慮事項です。オープンイノベーションは、内部資産の損失リスク、代理店コストと取引コスト、パートナーシップの管理コストを伴います。ヨーロッパの中小企業377社を対象とした調査の結果によると、オープンイノベーションは、少なくとも短期的には中小企業にとってコストがかかることが明らかになっています。
Kokubun, K. (2025). Digitalization, Open Innovation, Ambidexterity, and Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Narrative Review and New Perspectives. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202504.0009.v1
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |