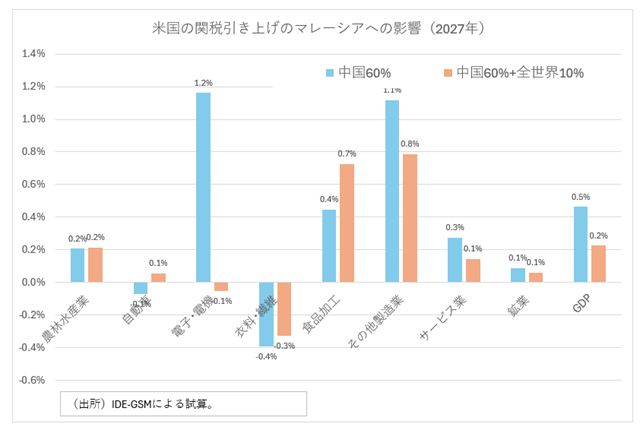第545回:イスラム銀行の普及のカギとなるデジタル銀行
Q: イスラム式のデジタル銀行の意義は?
A: 前回(544回)は、イスラム銀行の普及に関する若者世代を対象としたアンケートについて取り上げた。その中でイスラム銀行が身近にあるかどうかが重視とされることを指摘したが、重要なのは街の銀行とともに、オンライン銀行やネット銀行、デジタル銀行といったパソコンやスマートフォンで利用できる銀行の存在である。
2024年からマレーシアでイスラム式のデジタル銀行をてがけるイオン・ ファイナンシャル・サービスは、今年1月のニュースリリースの中で「店舗を持たない銀行であり(中略)アプリ等を通じて(中略)一連の工程が完結する金融サービスを提供」する銀行としている。マレーシアでは、五つの従来型銀行とイスラム銀行が順次開業することになっており、銀行の利用率のさらに高まることに期待がかかっている。
他方イギリスでは、何らかの形でインターネットにて利用可能な銀行は、およそ100行は存在するとみられているが、このうちイスラム式のデジタル銀行の有力4銀行が知られている。すなわち、カタール資本のアル・ラヤン銀行とカタール・イスラム銀行、およびクウェート資本のゲートハウス銀行とノモ・バンクである。これらの銀行はデジタル銀行という点で共通しているものの、個人向けに特化した銀行や企業向け融資を行う銀行、預金だけでなく不動産や債券などを対象とする投資型預金を行う銀行、英ポンドだけでなく米ドルやユーロ建で預金ができる銀行、そしてアプリから海外送金ができる銀行など、それぞれの特性に合わせた個性的な銀行となっている。
デジタル銀行が身近になるには、インターネットとデバイスの普及が必須となるが、近年はいずれの国でも大幅に高まっている。様々な金融商品・サービスの提供や、色々な方法でアプローチできるアクセス方法などの多様性が、イスラム銀行の普及につながると言えるだろう。
| 福島 康博(ふくしま やすひろ) 立教大学アジア地域研究所特任研究員。1973年東京都生まれ。マレーシア国際イスラーム大学大学院MBA課程イスラーム金融コース留学をへて、桜美林大学大学院国際学研究科後期博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。2014年5月より現職。専門は、イスラーム金融論、マレーシア地域研究。 |