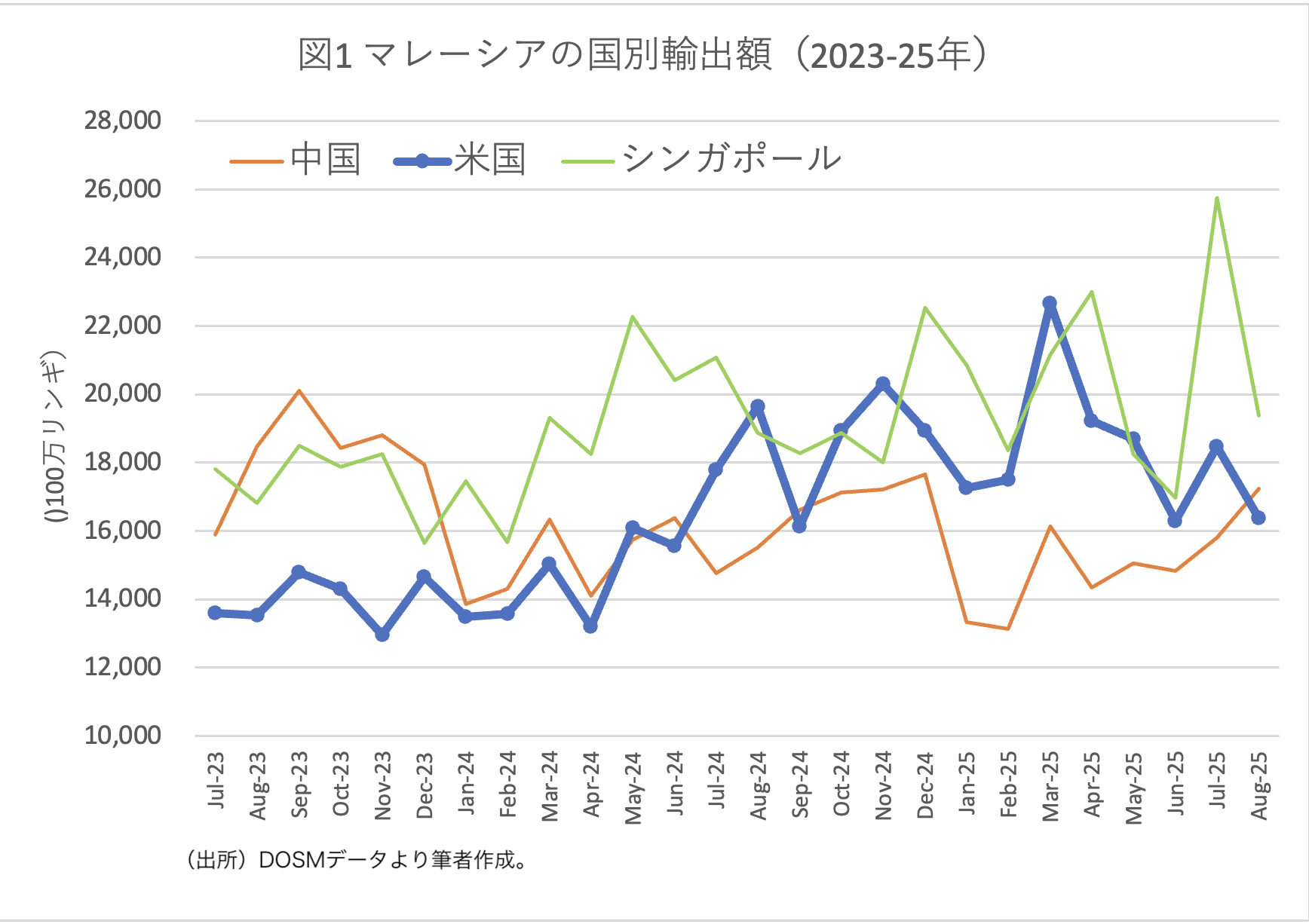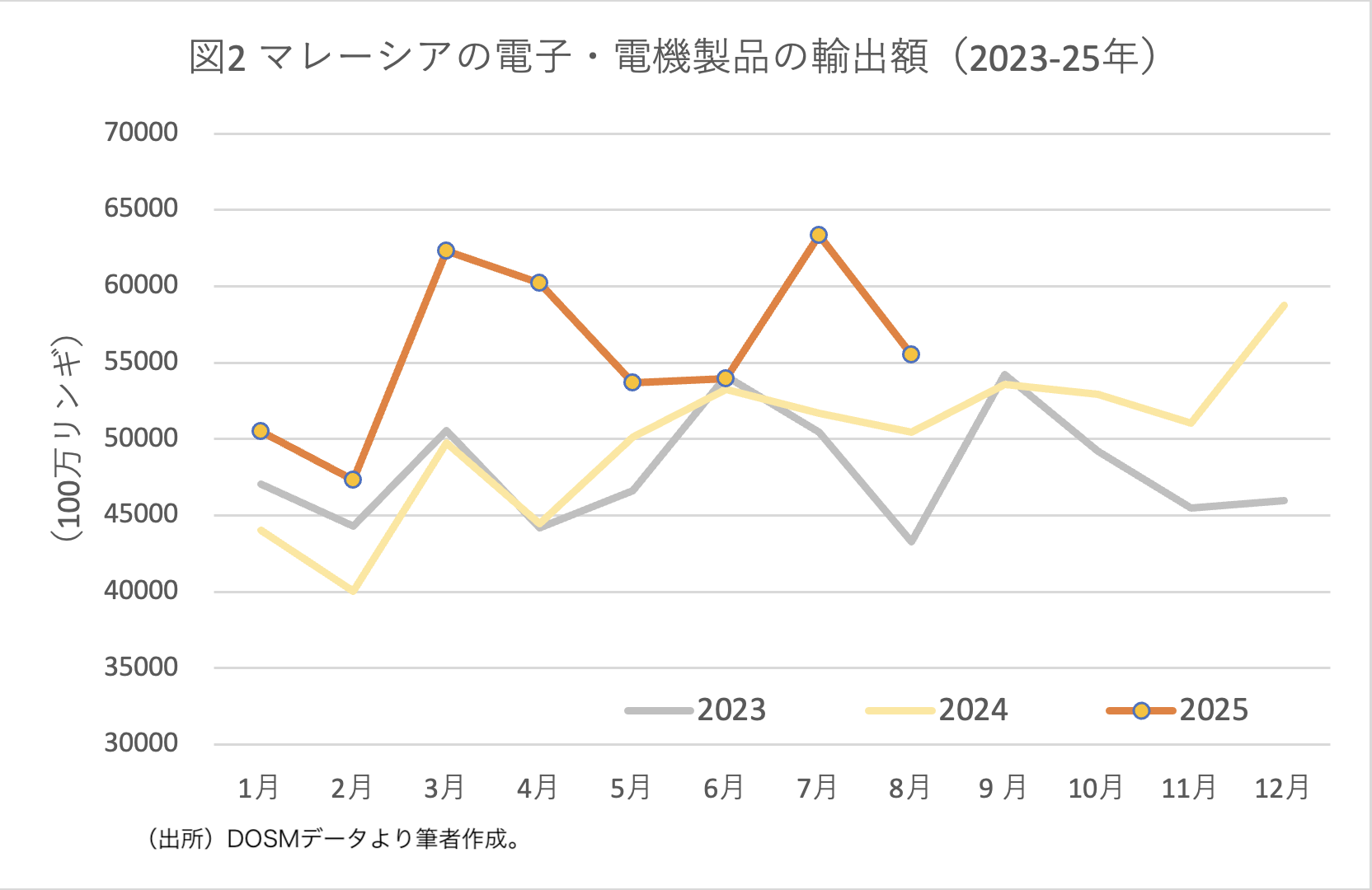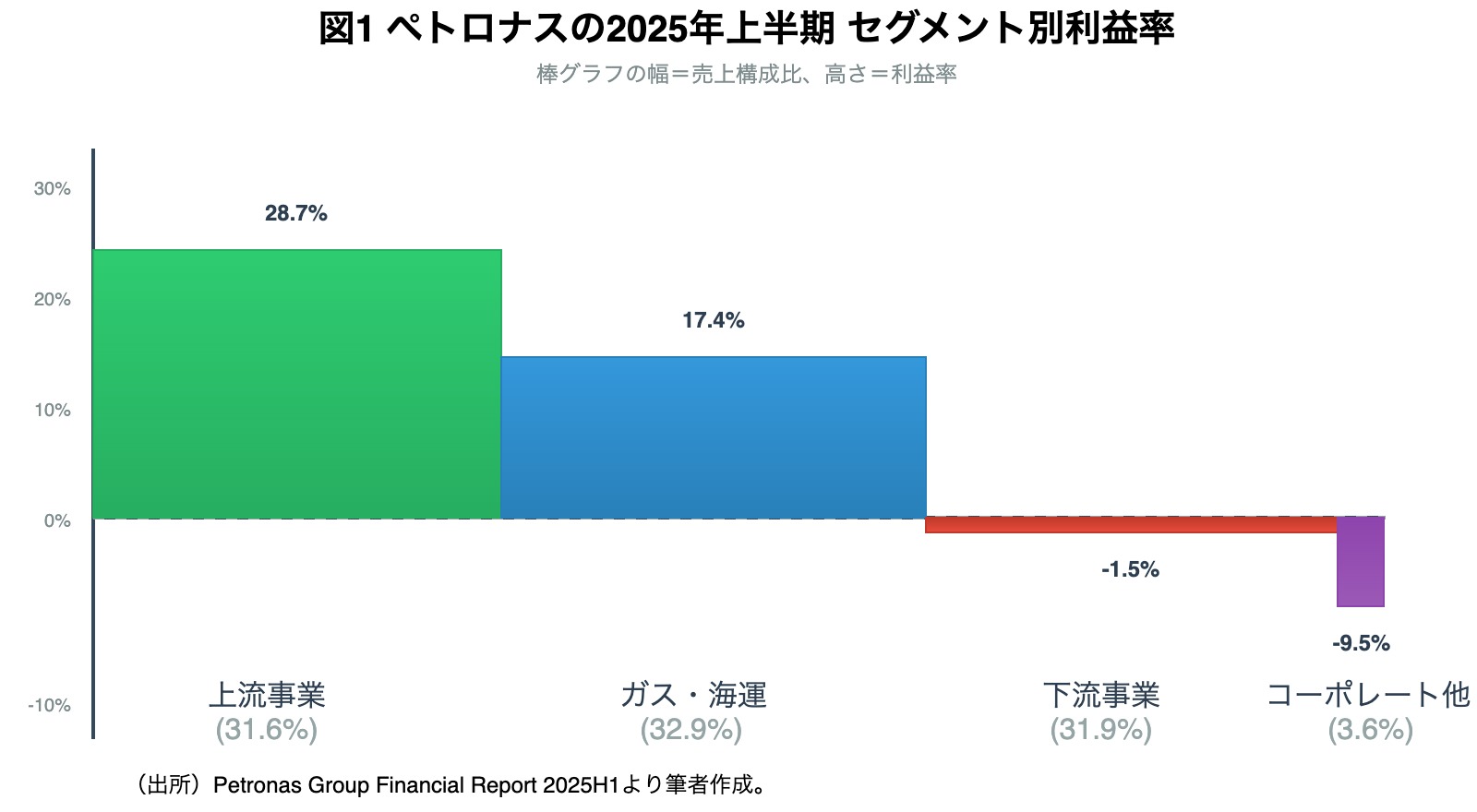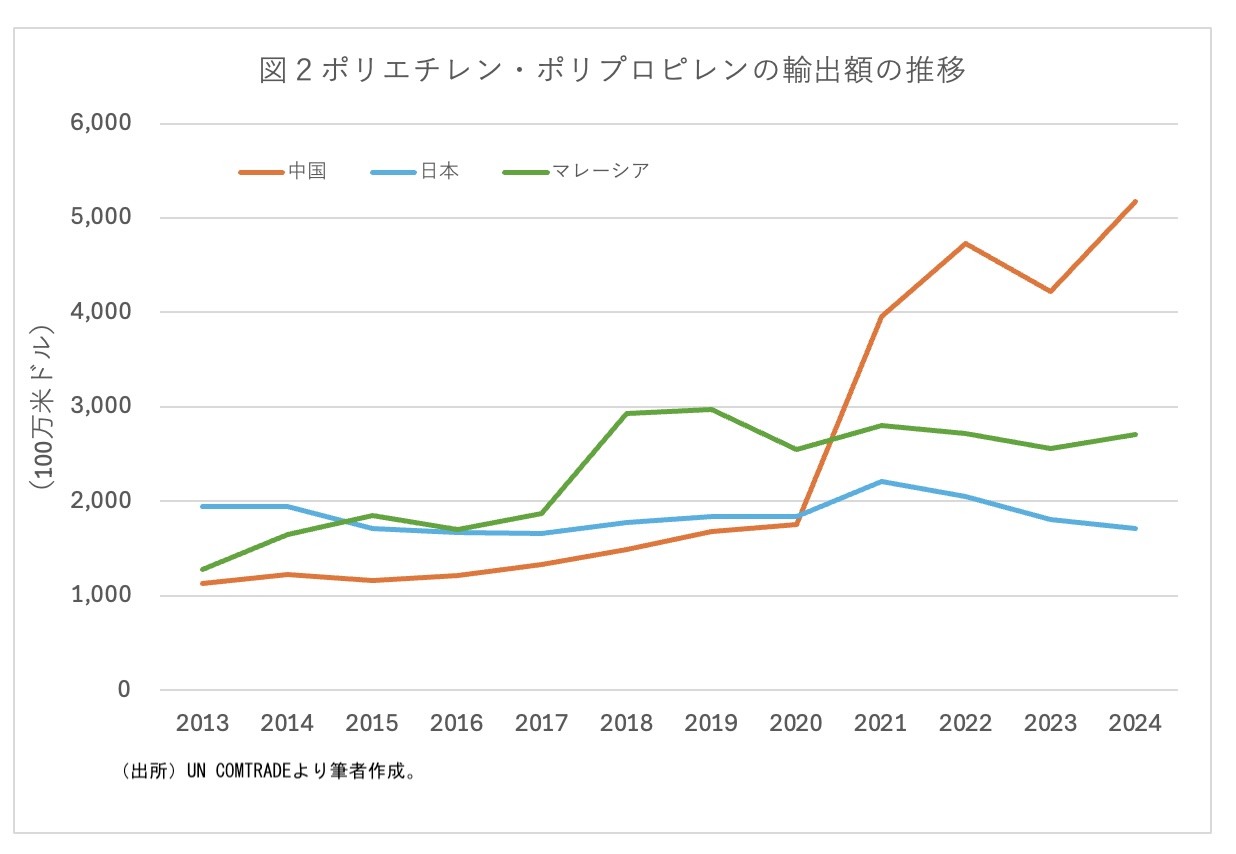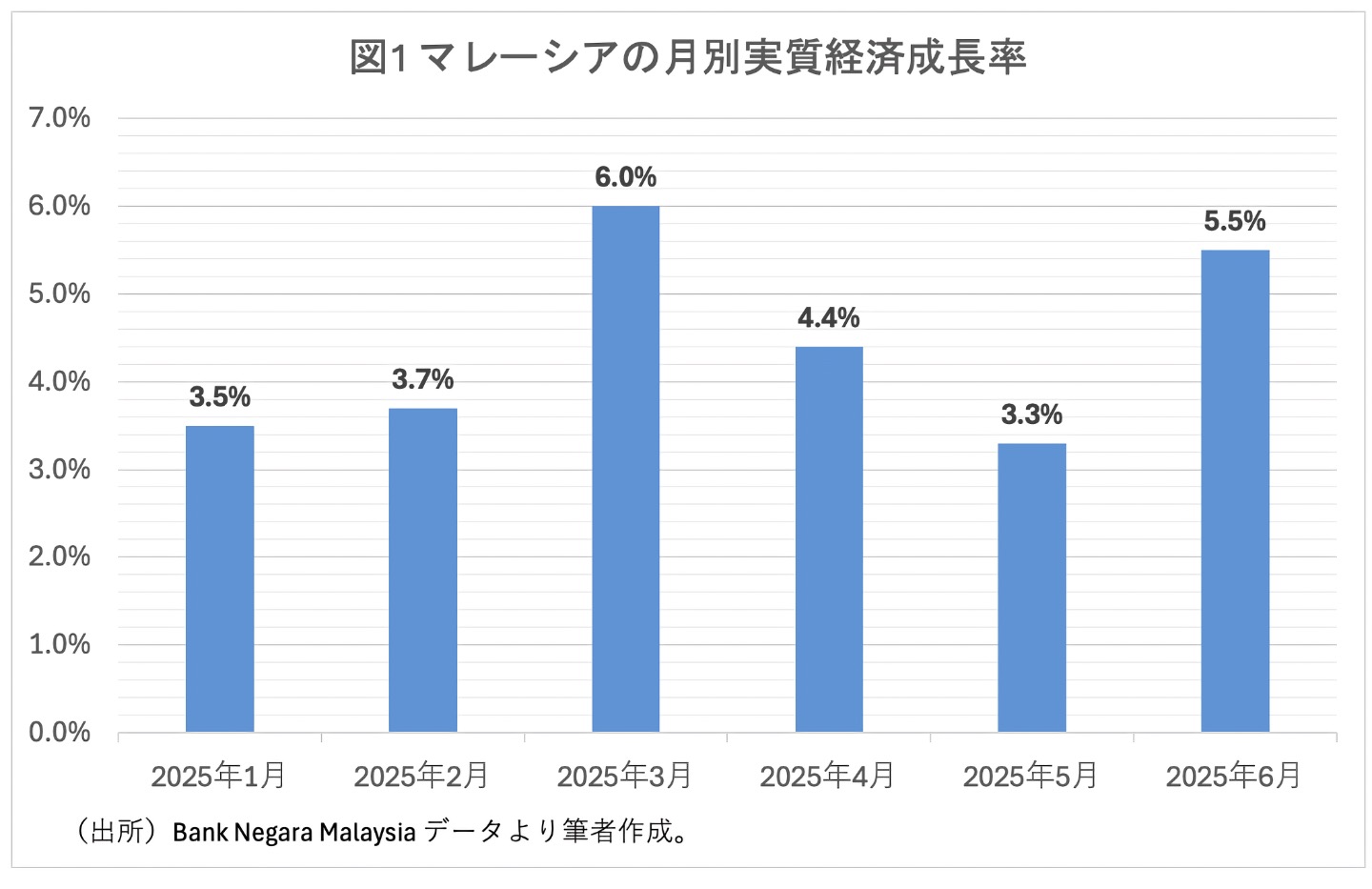第909回:中小企業の両利き経営(12)グリーン・イノベーションとオープン・イノベーション
前回は、財務資源を確保することで、企業は競争優位を構築するために必要なイノベーションに戦略的に投資することが可能になるというお話でした。今回は、グリーン・イノベーション(地球に優しい技術に関するイノベーション)とオープン・イノベーション(様々な主体との協力によるイノベーション)の関係についてです。
グリーン・イノベーションは、オープン・イノベーションを促進する可能性があります。なぜなら、環境に配慮したビジネス戦略を追求するには、中小企業がそうした活動に関心と知識を持つステークホルダーと連携する必要があるからです。例えば、エクアドルの中小企業543社を対象とした調査では、自然、気候変動、汚染、生物多様性、原材料・水・エネルギーの無駄の削減といった環境保護への取り組みは、外部の情報源(顧客、研究機関、ネットワーク、大学など)からの知識獲得、従業員の研究開発への参加、特許やロイヤリティの活用、競合他社との相乗効果やパートナーシップの形成といったオープン・イノベーション活動を促進し、イノベーションのパフォーマンスを高めることがわかりました。
一方、インドネシアの中小企業を対象とした調査では、オープン・イノベーションは多様なステークホルダーとの連携を促進することで、グリーン・イノベーションにプラスの影響を与える可能性があることが示されました。関連して、マレーシアの中小企業345社を対象とした調査の結果は、中小企業がオーケストレーションを通じて持続可能性と競争力のトレードオフに対処できる可能性を示唆しています。さらに、290人の中国企業幹部を対象とした調査に基づく研究では、社内の情報共有と社外との連携を強化することが環境イノベーションの促進に不可欠であると結論付けられています。
グリーン・イノベーションとオープン・イノベーションが相互に強化し合う正のフィードバック・ループを形成することで、企業の両利き能力や持続可能性が高まることが期待できます。
本連載記事に関係する論文が、以下のURLから全文無料でアクセス可能です(2025 年 11 月 13 日まで)。
Kokubun, K. (2025). Ambidextrous SMEs for a sustainable society. A narrative review considering digitalization, open innovation, human resources and green innovation. Next Research, 100839. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3050475925007067
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |