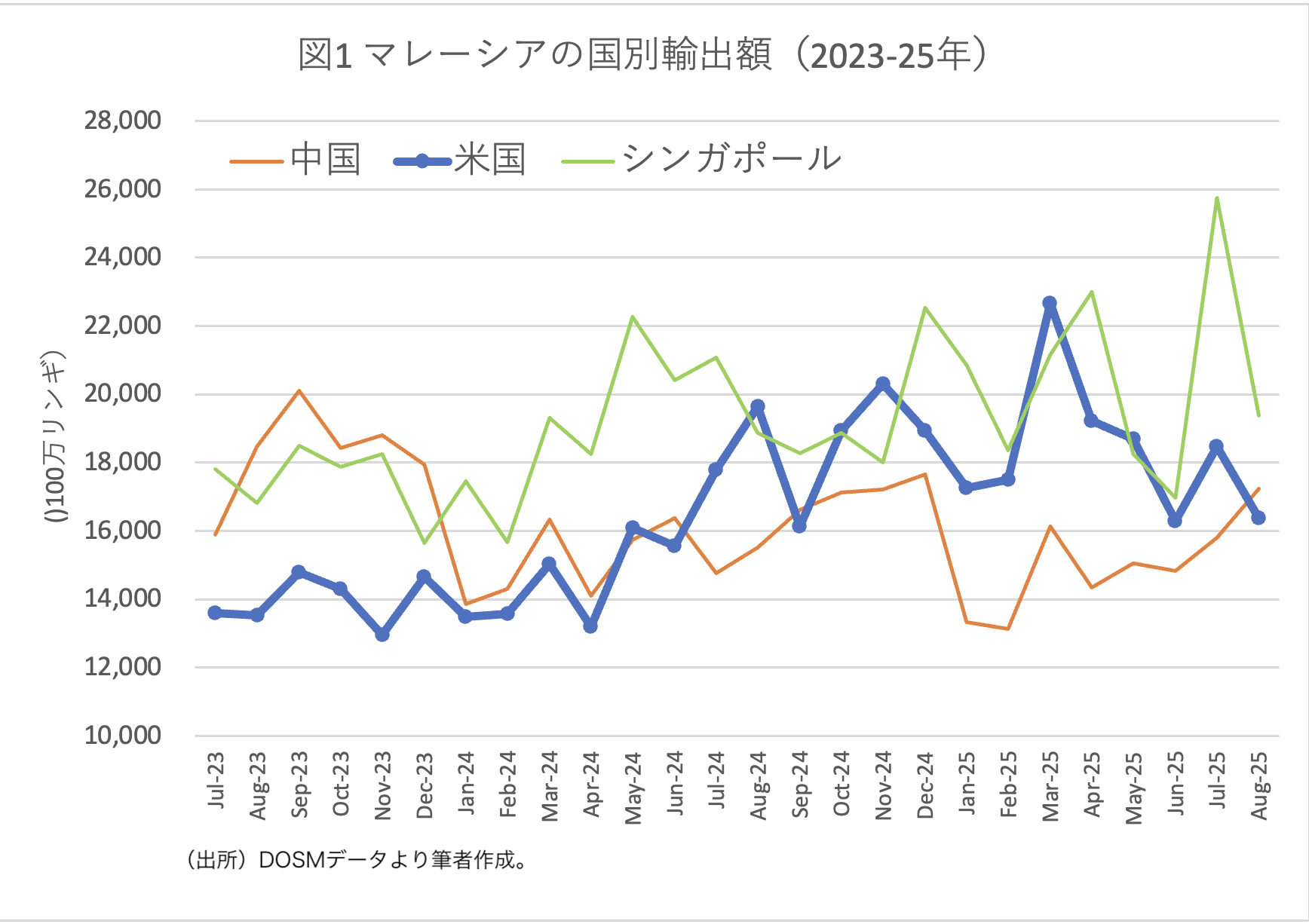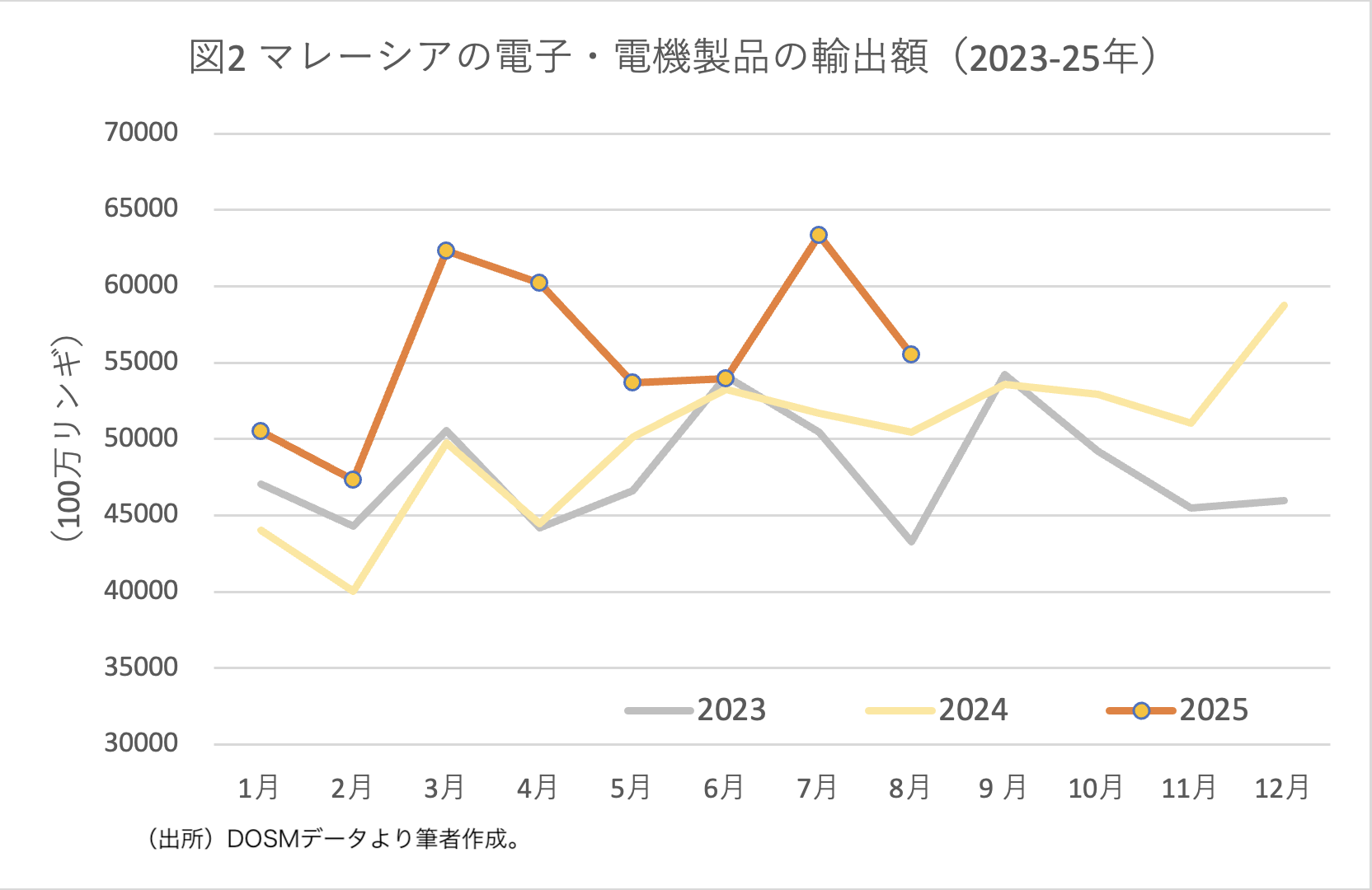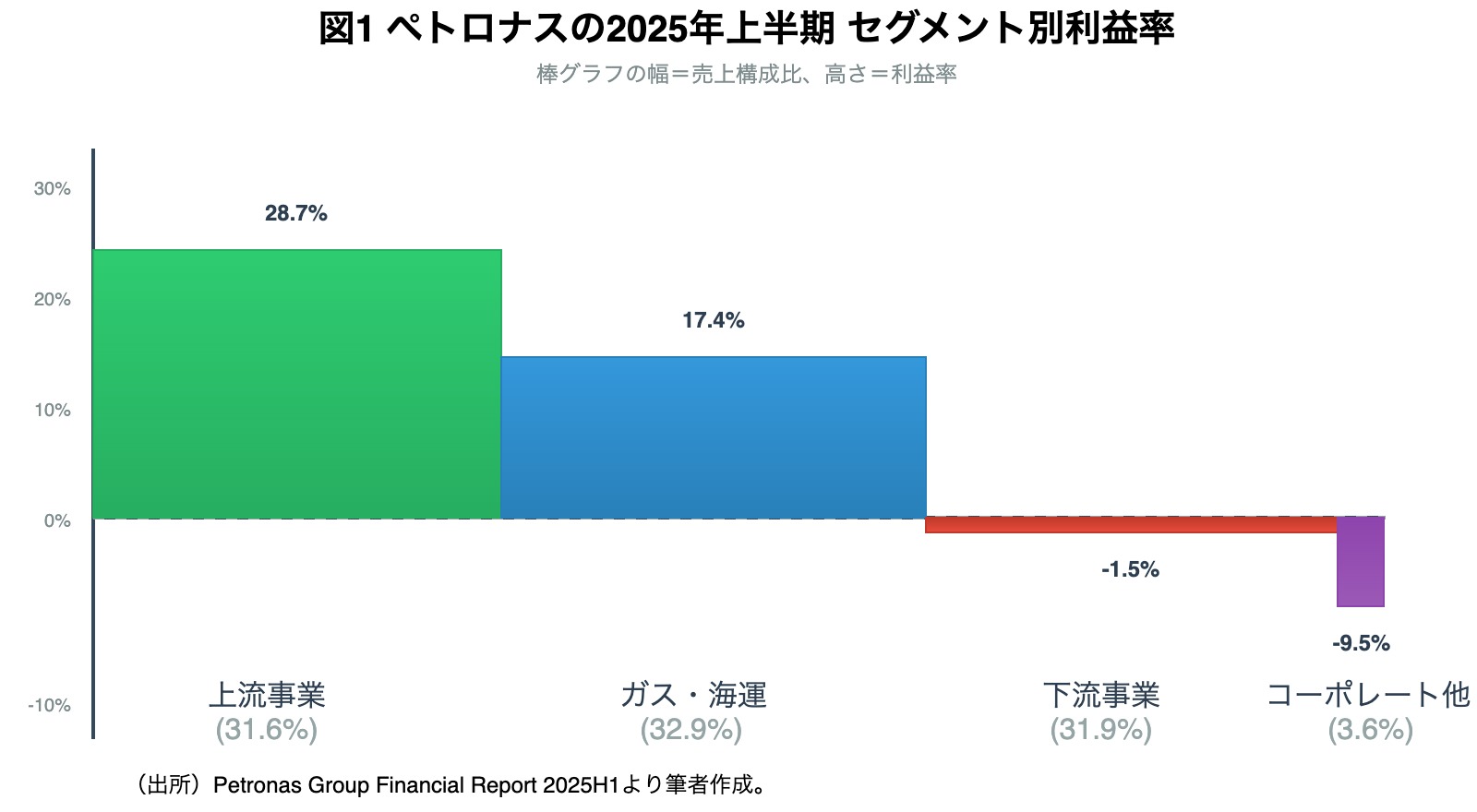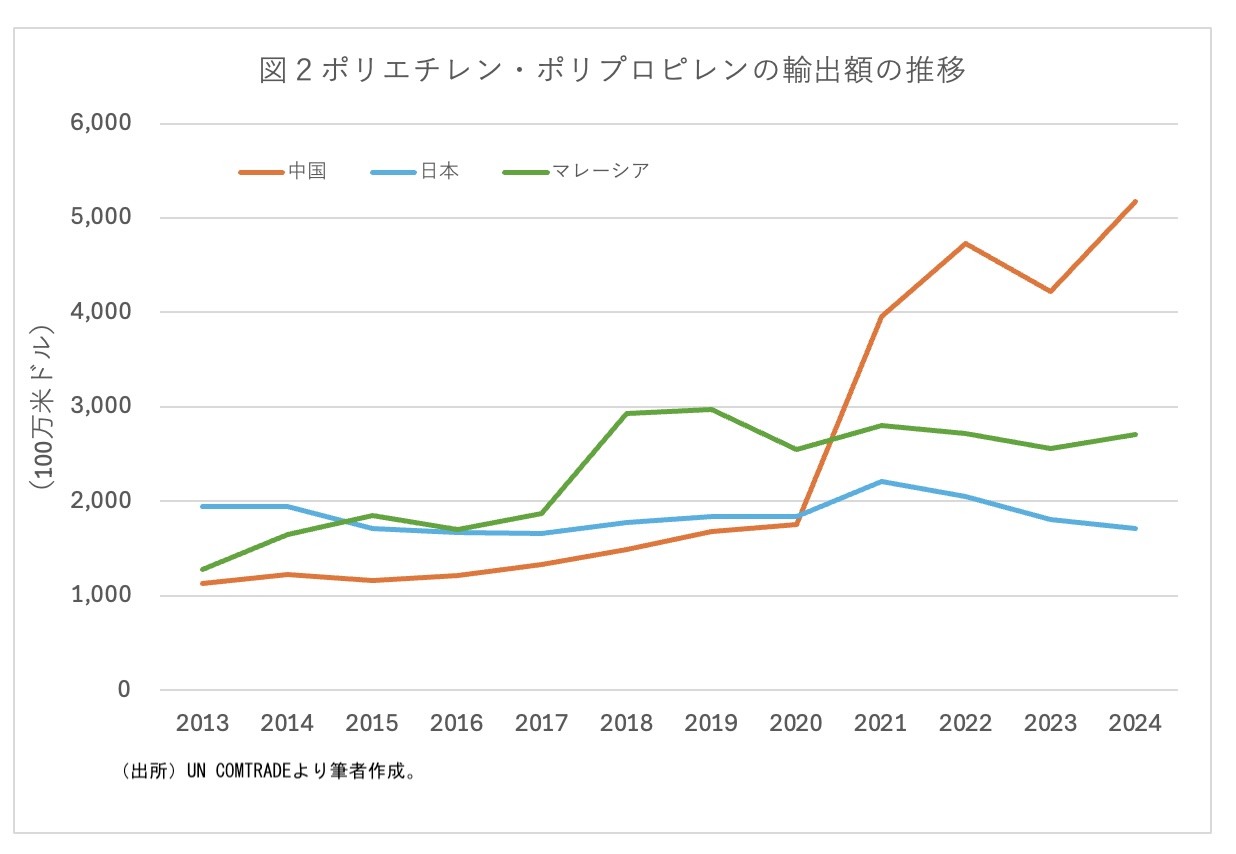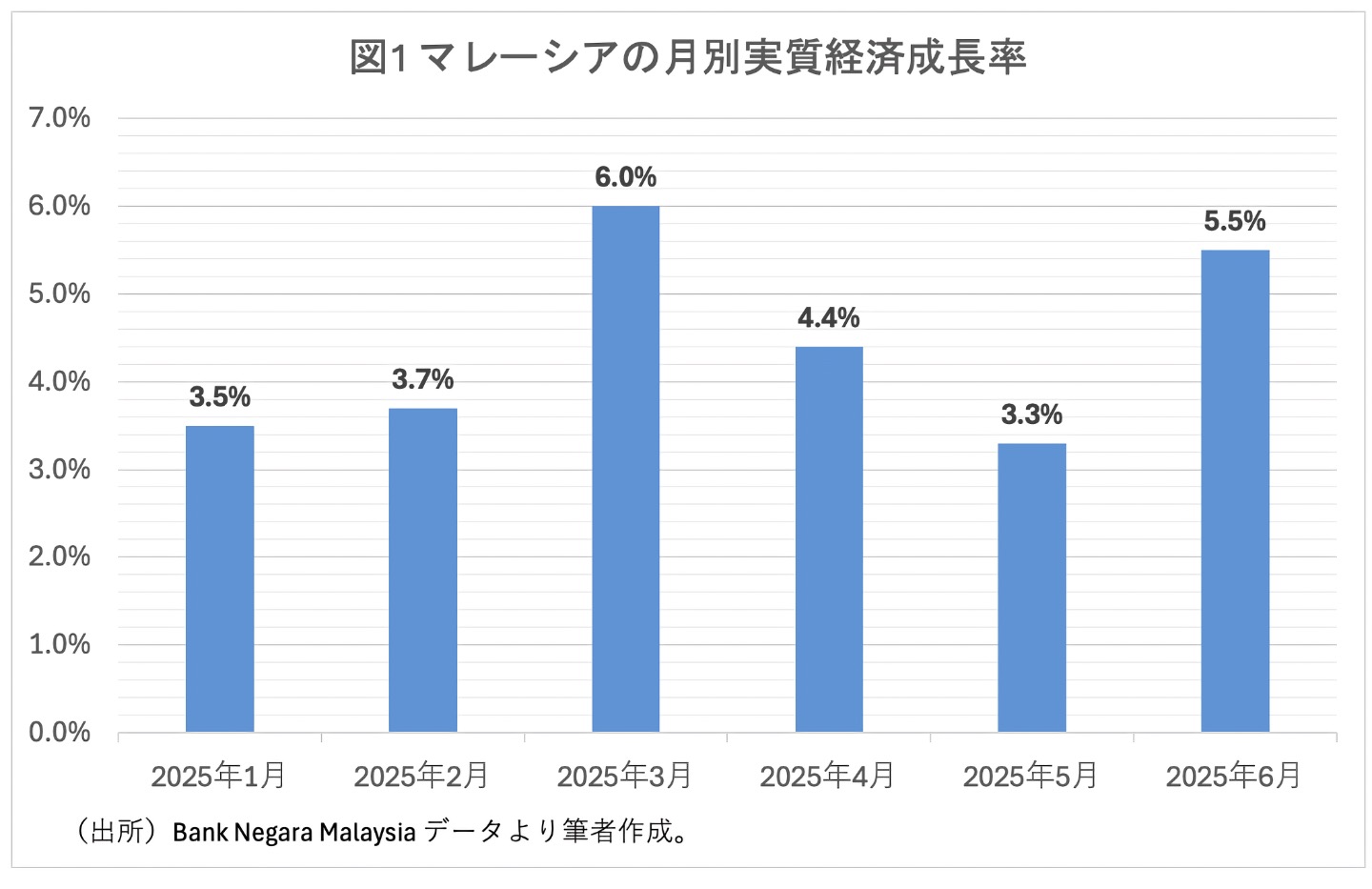第577回 FINDEX2025にみる東南アジアの銀行利用
Q: 世界銀行がFINDEX2025を公表しましたが、内容は?
A: 世界銀行はFINDEX2025を7月に公表した。これは世界中の人々を対象として、銀行の利用状況をアンケート調査したものである。これまで2011年・14年・17年・21年・24年とコロナ禍の2020年を除き3年おきに調査を実施しており、今回のFINDEX2025は2024年の調査結果の公表である。
東南アジアでは毎回、ブルネイと東ティモールを除く9カ国が調査対象である。なおミャンマーは、今回調査は行われなかった。
「銀行や金融機関に口座を保有しているか?」という基本的な質問に始まり、有無の理由やサービスの種類・利用状況などを、年齢・性別・居住地・学歴・職の有無といった属性ごとにデータを集計・公開している。また今回新たに、スマートフォンに紐付いた電子マネーの利用状況についても、詳しく質問している。他方、以前には問われた「宗教上の理由で口座を持たない」といった宗教関連の項目が、今回はなくなった。
データによると、2024年の世界の銀行口座保有率は78.7%で、前回2021年の調査に比べて4.9ポイント増加した。東南アジア諸国でこの割合を上回っている国は、シンガポール(98.0%)、タイ(91.8%)、マレーシア(88.7%)の3カ国であった。他方、平均値は下回ってはいるものの過半数が保有している国はベトナム(70.6%)、インドネシア(56.3%)、フィリピン(50.2%)で、ラオスとカンボジアは40%以下であった(ミャンマーはデータなし)。
2021年と比較すると、3年間で世界平均と同等以上に割合が高まった国はインドネシア、ベトナム、カンボジアの3カ国のみで、他の国は前回と大きな変化はなかった。コロナ禍以前より高止まっていた国、コロナ禍でも保有者が増えた国など、傾向に差が表れる結果となった。(次回に続く)
| 福島 康博(ふくしま やすひろ) 立教大学アジア地域研究所特任研究員。1973年東京都生まれ。マレーシア国際イスラーム大学大学院MBA課程イスラーム金融コース留学をへて、桜美林大学大学院国際学研究科後期博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。2014年5月より現職。専門は、イスラーム金融論、マレーシア地域研究。 |