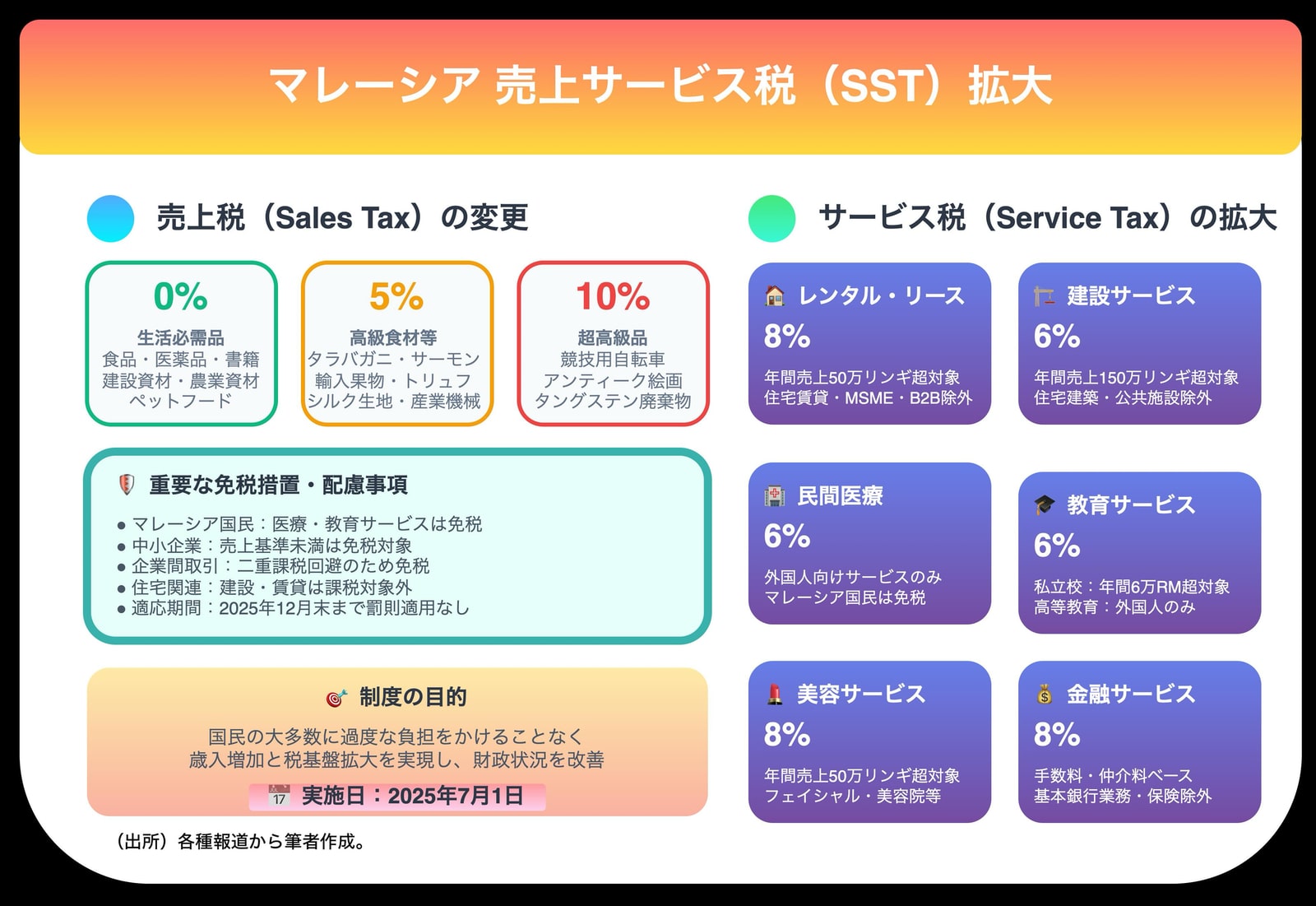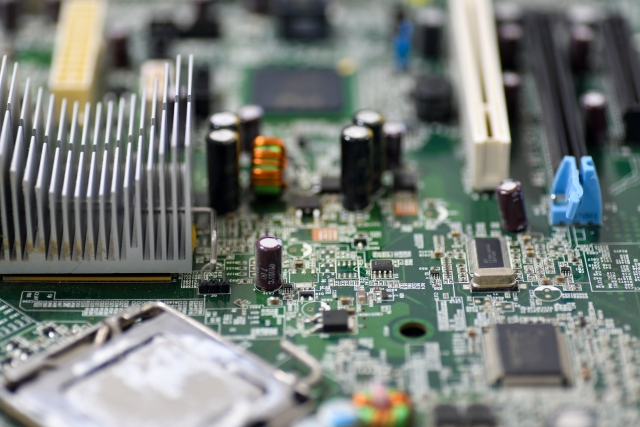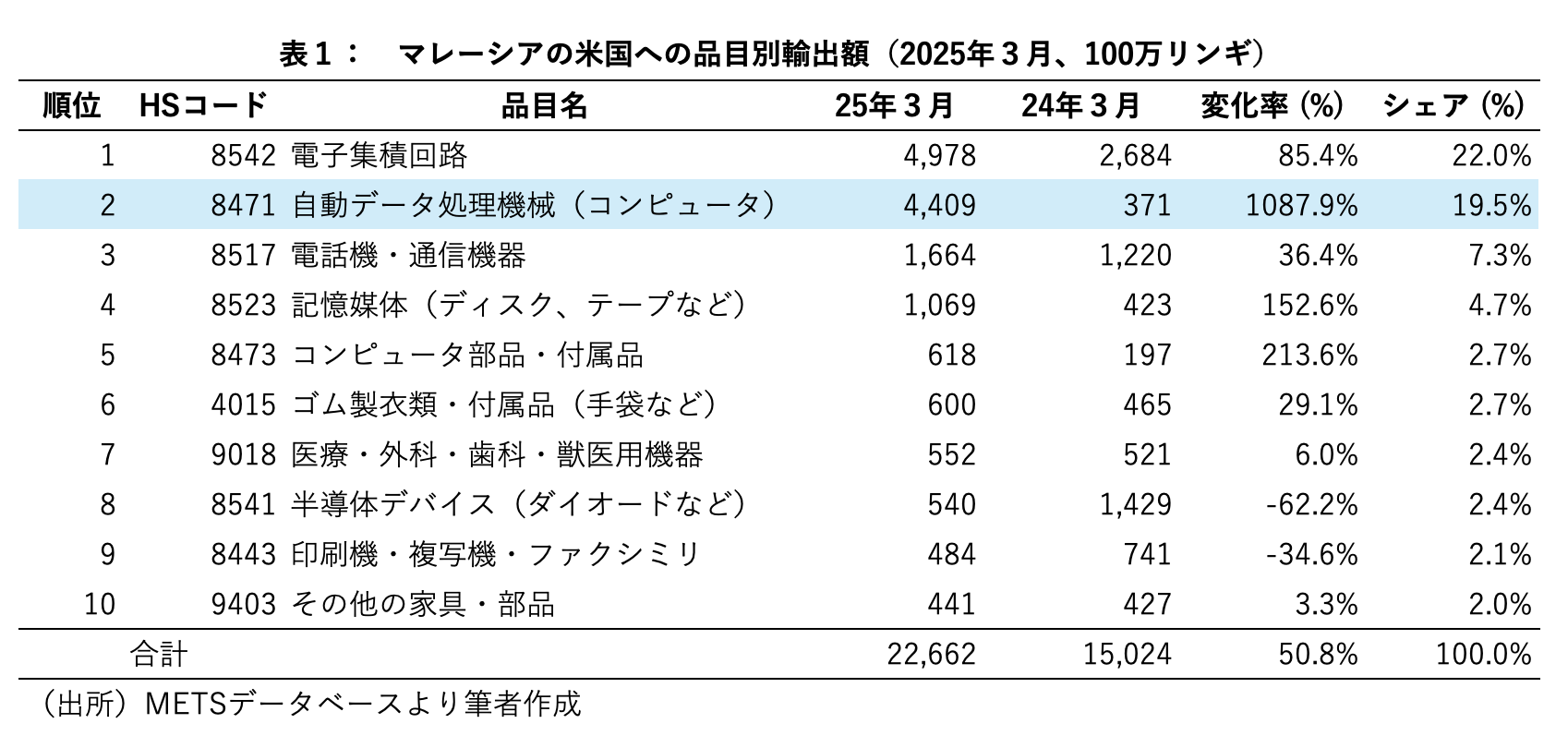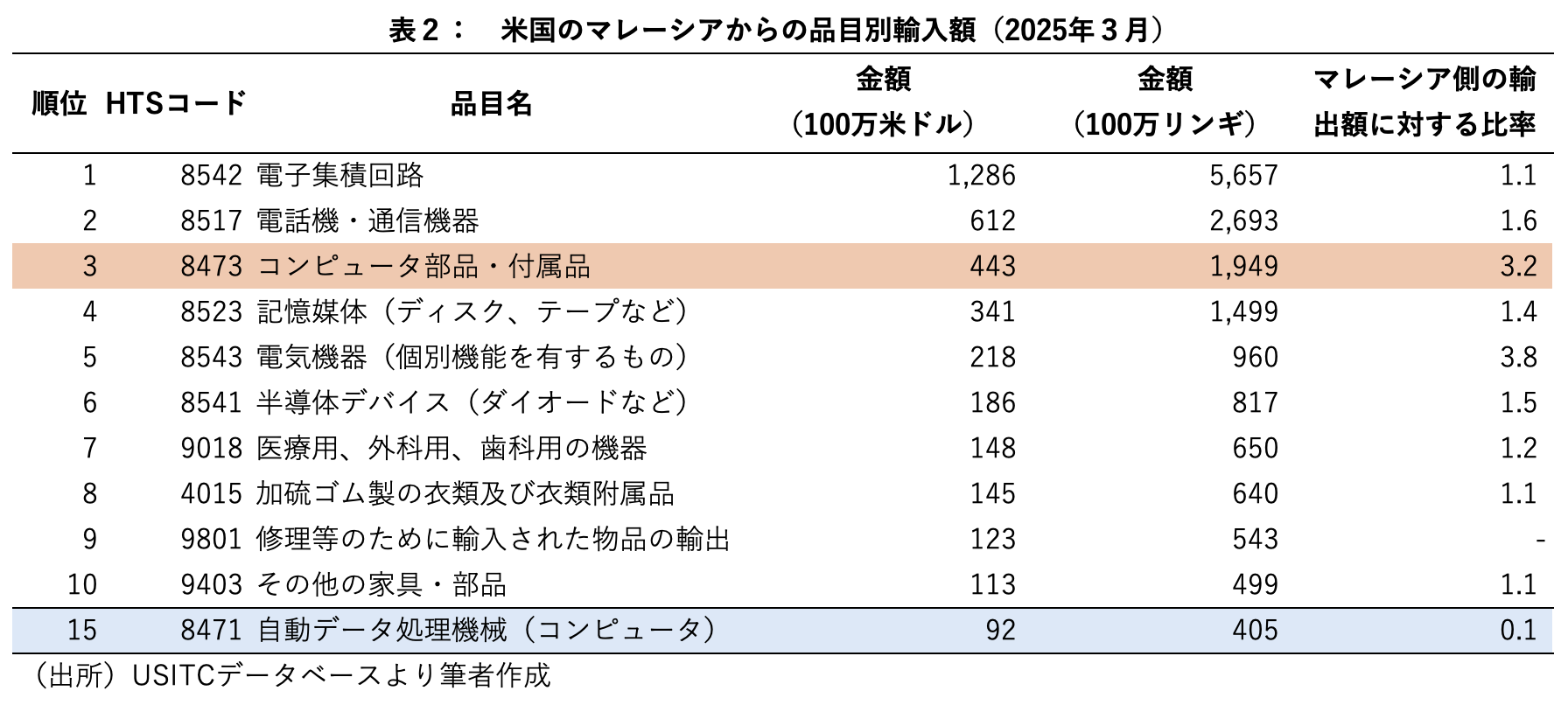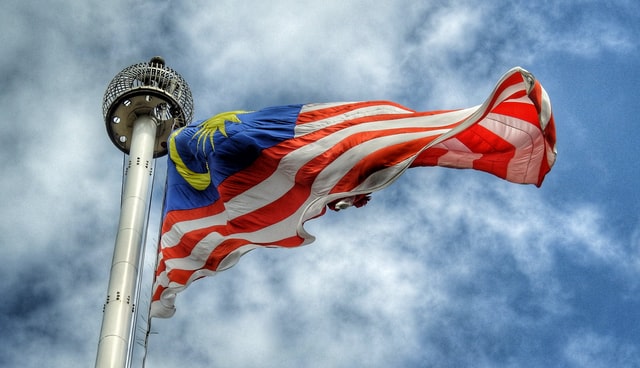第902回:中小企業の両利き経営(5)両利きと、長期的・地球的視点
前回は、中小企業の多くが深化を好むというお話でした。しかし、特定の技術に依存し、深化に特化することは、イノベーションと研究開発が牽引する産業において、時代の変化への対応を困難にし、競争優位性を低下させる可能性があります。今日、産業構造の転換により、ニーズの細分化、複雑化、予測不可能性が高まる中、中小企業にとって、下請け構造からの脱却や、既存のネットワークにとどまらない幅広い情報源の活用、技術シーズを機動的に新規事業に繋げるイノベーション活動がますます重要になっています。さらに、コロナ禍を契機としたICT化の波や、持続可能な開発目標(SDGs)を契機とした地球環境意識の高まりは、企業経営者に変化を迫り、従来のやり方に固執することのリスクを高めています。さらに、リスク分散、すなわちポートフォリオ投資の観点からは、国内で多くのイノベーション活動が展開されることが必要です。言い換えれば、両利きであることが一企業の短期的な売上に直接つながらないとしても、国全体、あるいは世界規模で取り組むことが合理的な場合があると考えられます。
さらに、両利きであることは中小企業にとって短期的には有益とは考えられないとしても、長期的には有益となる場合があります。深化と探索を組み合わせることで、中小企業は既成概念にとらわれず、短期的ではなく長期的な視点でイノベーションを起こし、最終的にプラスの結果を生み出す可能性があります。これは、両利きであることが、深化と探索という相反する要求を統合する上で重要な役割を果たすためです。両利きの中小企業は、斬新なアイデア、製品、プロセスを開発する能力を失うことなく、深化と探索を管理し、効率性を向上させる能力を持っています。
こうした中小企業は、財務構造に関する重要な意思決定を迅速かつ柔軟に行うことができます。例えば、国際化を通じて新たな市場を開拓したり、新製品や新ブランドを立ち上げたりすることができます。したがって、中小企業が両利きを達成できる方法を見つけることは、中小企業の回復力を高め、マクロ的または長期的な視点から、中小企業、国、そして世界が納得できる解決策に到達するために役立つ可能性があります。そこで、次回からは、中小企業が両利きを達成するための条件について検討します。
Kokubun, K. (2025). Digitalization, Open Innovation, Ambidexterity, and Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Narrative Review and New Perspectives. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202504.0009.v1
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |