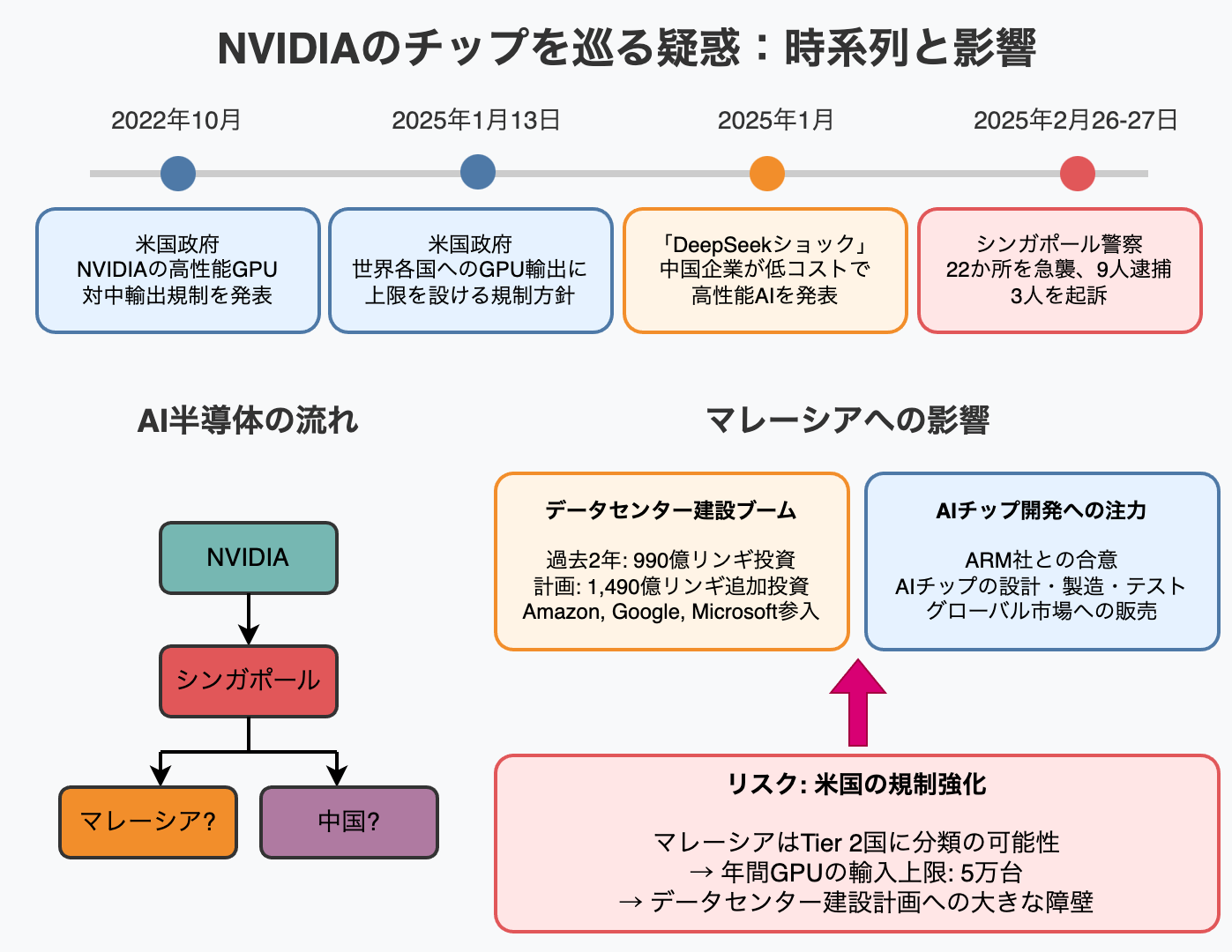第564回 エジプト、イスラム銀行市場が拡大
Q: 2024年のエジプトのイスラム銀行市場は?
A: エジプト・イスラム金融協会が3月に発表したところによれば、2024年のイスラム銀行市場は対前年比で60%以上の成長を示した。この背景には、近年のエジプトの経済状況があるようだ。
モハメド会長によると、同国のイスラム銀行部門の預金総額は7,380億エジプト・ポンド(約2兆1,700億円)で、対前年比で65%の増加し、従来型銀行を含めた全銀行の預金残高の7.3%を占めた。同様に融資総額も8,070億エジプト・ポンド(約2兆3,800億円)で対前年比64%増加、全銀行部門の融資の6%となった。現在エジプトでは、イスラム銀行専業銀行が4行、イスラム金融商品を扱える資格をもつ従来型銀行が11行存在する。専業4行とは、ファイサル・イスラム銀行、アブダビ・イスラム銀行、アル・バラカ銀行、そしてクウェート・ファイナンス・ハウス傘下の銀行で、いずれも中東・北アフリカの大手資本である。
このように好調なイスラム銀行市場であるが、近年のエジプトは20%を超えるインフレに悩まされている。一般的に、インフレ率の高まりは貨幣価値の下落を意味するので、中央銀行はインフレを抑えるため政策金利を上げる。市中銀行も、中央銀行に合わせて預金金利と貸付金利を上昇させる。実際、エジプトの従来型銀行の金利は20%を超えている。他方イスラム銀行は、政策金利に左右されずあくまでも実物資産の売買に合わせて手数料やリターンを決定する。もっとも、銀行間で預金や融資先の獲得競争が起きて、結果的に従来型銀行の金利と同程度の数値に収斂されていく。
なお、2024年の1年間でイスラム銀行の支店数は51店舗増え、全国で311店舗となった。これはおよそ20%の増加となる。イスラム銀行市場の拡大は、金融やマクロ経済の統計上の話というだけではなく、実体経済に根付いているといえよう。
| 福島 康博(ふくしま やすひろ) 立教大学アジア地域研究所特任研究員。1973年東京都生まれ。マレーシア国際イスラーム大学大学院MBA課程イスラーム金融コース留学をへて、桜美林大学大学院国際学研究科後期博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。2014年5月より現職。専門は、イスラーム金融論、マレーシア地域研究。 |